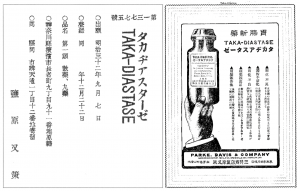高峰譲吉の妹、竹橋順子の随想録を紹介
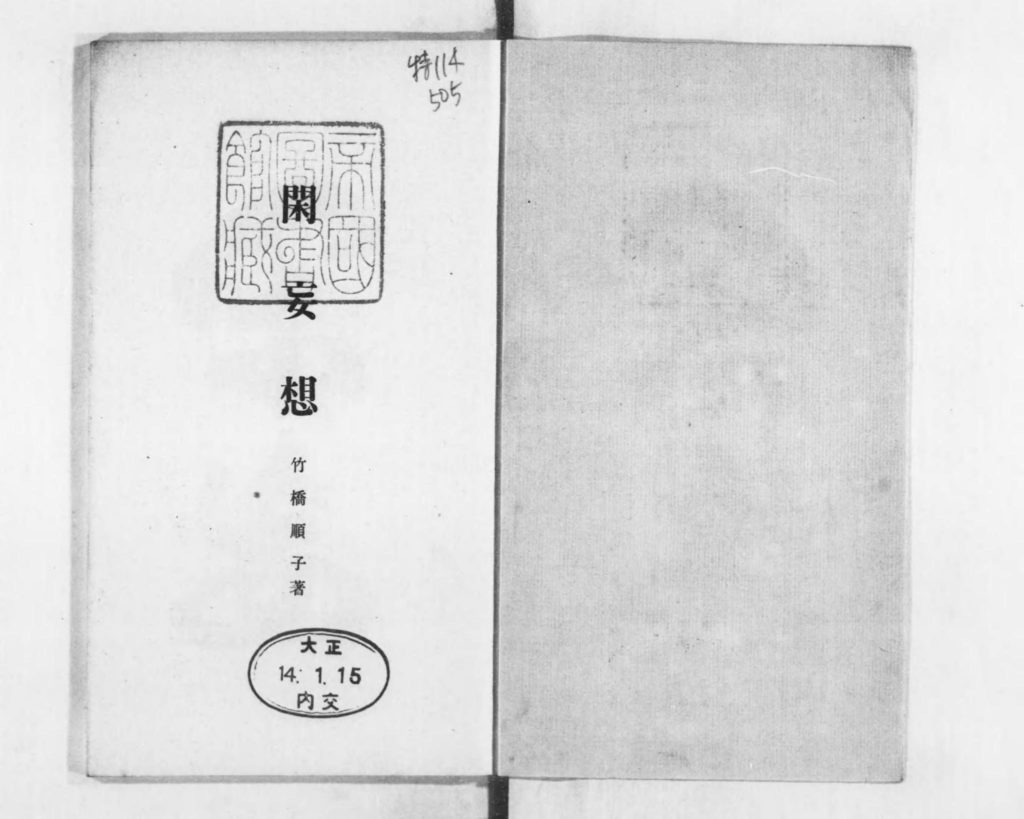
高峰家にはたくさんの兄弟姉妹がいました。その数、なんと13名!
譲吉は長子として生まれ、5人の弟と7人の妹がいたことになります。
前回、記事を公開した塩原又策が1926年に書いた「高峰博士」という書籍がありますが、そこには、退二、三郎、享一郎、修五、栄三郎の5人の弟と、節子、貞子、順子、十九子、十三子、せい子、五十子の7人の妹の名前が記されています。ちなみに又策には6男6女の12名の子どもがいました。
現代は少子化が問題ですが、この時代は多子家族が一般的にいたようです。
さて、今回は譲吉の妹である順子の著作について会員の方から貴重な情報を入手しましたので、ご紹介いたします。順子は1861年生まれの高峰家三女で、譲吉との年の差は7歳になります。
順子は、1922年に譲吉を米国現地で看取り、1925年に「閑妄想」という自身の随想録を出版しています。
「回想録」と「渡米日記」という二部構成になっており、そこには、自分の半生を振り返るとともに、兄である譲吉について身近な家族としての目線で記されており、とても興味深い内容です。
本文には折に触れて詠まれる漢詩や順子自身の人間関係なども記されていますが、譲吉に関連する記述を中心に引用し、意訳して時系列順に並べ替えて紹介していきます。
digidepo_920674_noBundleName出典:国立国会図書館デジタルコレクション(上記画像内で全文の閲覧が可能です。)
「回想録」より
自分は幼少より兄弟姉妹の中でもとりわけ父母の膝下で大恩を受け長らくお世話になりました。一人の兄(高峰譲吉)は12歳の時から長崎へ遊学に出られ、長姉は15歳で嫁入り、次姉は13歳で親戚に養女に参られ程なく先方で結婚しましたが、自分だけは、明治時代の開け行く恵みに浴して、加賀金沢に初めて女子の小学校が創立になり、13歳の時に入学して学びの窓に勤しみました。(P.10)
16歳の夏に、東京虎ノ門の工学寮に在学中の兄が初めて金沢に帰省をされた時、帰京の際に自分も同道上京して、湯島お茶の水の女子師範学校の入学試験を受け、9月に入学許可となりました。(P.11)
この年は、1877(明治10)年だと思われますが、新橋-横浜間の鉄道が1872年に開通してからまだ5年、金沢までの鉄道は開通していません。兄の譲吉について上京したと書かれているものの、どのようなルートで東京へ行ったかはわかりません。ただ、いずれにせよ兄妹での旅路であり、妹の入学試験に寄り添う兄の姿を想像すると、科学者や起業家といった譲吉のイメージとはまた違う趣が感じられます。
お茶の水女子師範学校では5年間の寄宿舎生活を経て卒業後、両親のもとへ戻り、石川県富山女子師範学校で教鞭を1年間とりました。当時、自分は年頃であったため縁談の申し込みがいくつもありましたが、長し短しで自分の理想にかなう縁談はなく、みんな断ってしまいました。兄は洋行中(米国ニューオーリンズの万国博覧会に事務官として派遣)であり、家事の手伝いや弟妹の世話、裁縫やら音曲に遊ぶやら、学問以外に女の道を一通り習ってるうちに4,5年が経ってしまいました。(P.11)
そうこうしてるうちに妹は18歳になり、知り合いの有名な商家から「ぜひ妹を嫁にくれ」と申し込まれ、断るに断れず両親は「姉が先に片付かぬのに妹は差し上げられぬ」と答えたのですが、それなら婚約だけして、姉が片付くまで待っていますと言われて妹の婚約が成立してしまいました。(P.12)
自分の身を改めて考えてみれば、両親に対して申し訳が立ちません。自分の理想が高すぎ、虚栄心にあこがれ、あそこは不十分、ここは気に入らぬと高い望みばかりしてるから、年齢ばかり嵩んで次第に良縁が遠ざかってしまいました。(P.12)
そこで決心し縁があった竹橋家に嫁ぐことにしたのですが、自分の夫と定めた竹橋尚文は陸軍中佐で3人の娘と1人の男子を残して妻と死に別れ、後妻を探しているところでした。(両親は猛反対しましたが)いかなる困難があってもご心配はかけず泣き言も言わず、4人の子は立派に養育し妻たる道を通しますと言い切って、両親もようやくこの結婚に承知をしました。(P.12)
それから20余年、波風も起こらず幸福に月日を送り、3人の娘はそれぞれ良縁に恵まれ嫁いでいき、息子は士官学校へ入学をして、夫婦ともども安心して喜び合いました。夫はこの間立身出世し陸軍中将となっていましたが、1906(明治39)年に突如亡くなってしまいました。自分の精神の打撃は極限に達し、これが禅道にはいる切っ掛けとなったのです。(P.13)
夫の竹橋尚文が亡くなった時、順子は40代半ばでした。尚文の死後、再婚はせずに禅の道に入り、そのまま生涯を過ごしました。
場面は変わって、1922(大正11)年の2月。譲吉は前年の12月から腎臓炎が再発し、一時重体となったもののなんとか持ち直しており、順子に一通の電信を送ります。
「渡米日記」より
自分の兄の高峰譲吉が米国に30年移住して日米の親交を図り、また薬品その他の発明を成して世界のため、日本のためにどれほど貢献したかと思いますが、この2,3年はとにかく病魔に侵されいました。最初は心臓を患い、昨年秋ごろから全快し健康になったのものの、ワシントン会議中で何かと国家のために奔走し身体に無理がきて、ついに12月15日から急性の腎臓炎で一時相当の苦痛を感じ重体となってしまったが、何とか快方に向かいました。(P.25)
しかし、なかなかの大病であるため、妹である自分に渡米して、看護をしたり日本の話をして慰めてくれぬか、と大正11年2月の中頃に電信を送ってきました。そこで自分は、喜んで参ります、今月の末にでもすぐに支度して出発します、と返信したところ、病勢も幾分か治ってきているので5月ごろに到着するつもりで出立してくれとの再度の返信が来ました。(P.26)
この頃、譲吉が順子にあてた手紙について触れている別の手紙があるので紹介します。
この手紙は、譲吉から親族の木津太郎平(後の高岡市長)に宛てたもので、自身の現状と妹の状況を訪ねる内容になっています。太郎平は1875(明治8)年に高岡市の廻船問屋木津家に生まれ、祖母が譲吉の伯母であったことから、譲吉から多くの薫陶を受けました。1919(大正8)年には譲吉がアメリカのアルコア社と合弁で設立した東洋アルミナムにも参画しました。
以下、手紙の意訳です。
木津太郎平様
拝復
貴方様におかれましては、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素よりご無沙汰しておりまして、お許しください。私の病状につき、お問い合わせを賜り、ご親切、感謝の至りに存じます。
実は昨春来、気分が悪かったのですが、療養の結果、夏頃には殆んど完治しておりましたところ、先般、実業団の渋沢子爵、その他ご一行が(ニューヨークに)来市された際に過労を覚えて、昨十二月中旬頃より床に伏しており、目下療養中であり、一時は皆様にご心配して頂きましたが、ただ今にてはお陰様で非常に軽快であり、この分であれば遠からず全快すると予想しておりますので、私のことはご心配はご無用に存じます。
渋沢子爵とは高岡にて親しくご面会する機会を得て、長らく細々としたことまで話し合いました。その際、私に対し帰国の意思を翻して米国の土となる決心で、日米の為に尽して欲しいと説得されました。私も過去三十年余り(日米親善に)尽力してきましたので、それを捨てて帰国する理由も見い出せず、いずれにしろただ今はそのように決意を致しております。
以上のような状況ですので、先年来計画している今春の帰国は難しいですが、今秋には健康が許せば一度帰国したいと思っております。あしからずお含みおきください。種々ご心配をお掛けしておりまして、重ねてお詫び申し上げます。
先般、愚妹の順にこの際米国見物がてら来航するように申し付けました。どのような都合かと案じております。
石黒博士は達者であられたのにご逝去されたと聞き大変驚いております。想えば石黒氏とは若年時代よりの知己であり、一層感極まり、哀悼の意に堪えません。ご家族ご一同はご健勝でしょうか。よろしくお伝えください。
なお時節柄ご自愛専一にお祈り申し上げます。愚妻よりも特によろしくと申しております。実は昨年冬より病気にて引き籠っておりますが、昨今は殆んど快癒しておりますので、これまたご心配はご無用に存じます。
まずは右、お礼かたがた、お考えをご教示いただきたいと存じます。
敬具
大正十一・一九二二年二月七日
高峰譲吉
文中の石黒博士とは、石黒五十二のことで英国グラスゴーへともに留学し、同じ大学に通った仲ですが、この年の1月に逝去していました。自分の体調は大丈夫であると伝えると同時に、寂しさや不安が読み取れる手紙の内容だと感じます。ちなみに、石黒五十二・すま夫妻の孫の一人が昭和30年代に大活躍したテニスプレーヤー石黒修、その子が俳優の石黒賢です。
さてさて、順子の著作の引用に戻りましょう。
出発は5月を予定していましたが、兄の病魔は中々にしつこく病勢は一進一退の有様で、(米国の)家族より万が一のことがあってはと、やはり船の予約が取れ次第渡米してほしいと電報が届き、兎にも角にも4月17日の太洋丸で出立することにしました。同行は、三共株式会社の技師である上中啓三氏と兄の秘書をして長年高峰家のために尽くしてくれている田口一太氏です。上中君は17年も米国に居住して兄が「アドレナリン」を発明した時の補助役をなされ大に貢献されし方で、今回も薬品の製造に関係して兄の依頼で渡米することになったのです。(P.26)
上中啓三は、改めて説明するまでもありませんがアドレナリンの単離抽出・結晶化の実験を実際に行った譲吉の助手です。東大の長井長義教授から紹介を受け、譲吉がアメリカに呼び寄せました。啓三の功績があったからこそアドレナリンが世の中に広く出回ることになりました。
大正11年4月17日、四谷の自宅を出発し、東京駅発横浜波止場行の汽車に乗りました。海岸へ汽車が着くと、すぐ目の前に見上げるばかりの巨船が岸壁へぴたりと横付けになって大梯子で人々を船中に送り込んでいます。これが自分を載せていく太洋丸です。
船中に乗り込み、船室に入り手荷物を調べた後、見送りに来られた人々に挨拶をなさんと甲板に登り陸上を見回すと、岸上には人が充満し、見送る人と見送られる人、岸と船とが呼応し、手を掲げ、ハンカチーフを振り、別れを惜しむ人情は上下の差別なく皆一様であります。
自分を見送ってくれた親戚、知己、朋友の多数也氏を心に感謝していると、太洋丸は汽笛を鳴らし徐々に岸壁を離れ、今や海外へ向けて進行を始めました。自分のへその緒を切ってから初めて日本国を去り、外国へ旅立つ門出です。(P.28)
船は次第に進行し、岸上の見送り人も豆粒のごとく小さくなり、港口近くに進めば、此度ご来遊の英国皇太子殿下の旗艦を始めとして護衛の任に当たる我が国の艦隊も前後左右に整然と列を正して碇泊しています。その間を太洋丸は徐々と進んでいきました。自分の船室の相客はドイツの婦人で、横浜に17年間も居住した人でした。米国を経由してドイツに帰るとのことで、日本語も喋ることができ、自分にとっては好都合でした。
しばらくして同行の田口君と甲板に上がり見渡せば、東京湾の入り口にて富津の海保や観音崎の灯台がだんだんと遠ざかり、左に房総の山々が薄霞み、右を見れば湘南沿岸の翠の峰も暇を告げ、伊豆半島や大島群島も見えなくなった後、自分たちも船室に戻り休息をとりました。(P.29)
田口一太は、秘書として最後まで譲吉に仕え、いろいろな事業のサポートを行いました。譲吉の遺言状に一太への分配分が記載されていることからも、その信頼の深さが見て取れます。ずいぶん前になりますが、2011年に研究会の山本綽元理事長が北海道のシンポジウムに参加した際、譲吉の関連講演が聖心女学院札幌校で開催されました。この女学院の校長先生が、一太のお孫さんだということがわかり、お互いに驚いたことがあります。1916年に譲吉が来日した際、一太の挙式を高峰夫妻が媒酌人を務め行ったという情報を伺いました。
さて、一行は5月3日にサンフランシスコ港に到着。汽車による陸路でシカゴを目指します。カリフォルニア州サクラメント、ネバダ州リノ、ソルトレイクシティ、ワイオミング州、ネブラスカ州ジュールスバーグ、オマハを通り、5月8日にシカゴに到着しました。
今一夜を明かせば、明日はニューヨーク着となれば心中の嬉しさは何にも代えがたく、さらにシカゴホテルには高峰から二通の電信が来ており、無事の旅行を祈るという内容と、自分だけはニューヨークに着いたらすぐに兄上の家に来い、とのことでした。
病気の兄の気持ちを思えば、一夜とて千秋の思いで何とも言えぬ嬉しみと病状如何の心配とが交互に湧いてきて、今回の長い道中を保護同伴してくれた田口、上中両君に明日は袂を分かち、別々の道に向かうと思えば、盲者が杖を失う心地です。さらに兄の家では、家族中で病兄のみ言語は通じるが他はみな日本語に不通なりと思えば、悲喜交々至って何とも言えぬ感じがしています。(P.46)
5月9日朝9時40分、ついにニューヨーク停車場に安着。高峰家より襄吉、孝の両夫婦を始め、事務所および研究所員の方々一行が自分を出迎えられ、一々握手を交え、自分は襄吉夫婦と自動車に同乗して、ニューヨーク郊外ニュージャージー州パセイクの高峰邸に到着しました。(P.26)
(兄と妹の久しぶりの再会は)一日千秋の思いで互いに待ち焦がれしこととて兄も病苦を忘れて喜ばれ、感極まって互いに涙のみでした。(P.26)
後で聞けば兄上には前日まで自分共の着米を秘してあったとのこと、それは長き道中を行くのであるから病人が待ち遠がり心身を労しては体に障るとの姉上の注意から、明日到着というまでは言わずに置いたとのこと。病気につき、万事姉上の注意は真に至れり尽くせりで自分も涙とともに感謝すること多大であった。(P.27)
本文中に記述はありませんが「姉上」とは譲吉の妻・キャロラインのことを指していると考えられます。キャロラインも日本で過ごしていた時期がありますから、順子とキャロラインは何度か顔をあわせています。表現の端々から、キャロラインに対する信頼と敬意が読み取れます。
爾来、6月7日まで姉上や看護婦とともに病室に出入りして病人を慰め看護の手助けま又は病人の苦痛の箇所を撫でたり摩ったりしていましたが、病勢は相変わらず一進一退なりしも自分の着米後は日々良好の結果で、親友の岡田博士も度々見舞われ、昼食だけは日本食であるから、厨房に行って料理人とあれこれ病人の好む物を調理して兄を喜ばせました。(P.27)
この分であれば全快して共に帰朝の望みもあるかと喜んでいたのも束の間で、ついに主治医から全快の見込みはないとの宣告を受けました。
姉上が言うには、日々の苦痛を見ながら死を待つのも残念だから知人のドクターが経営するレノックスヒル病院に入院させて尽くすだけの治療を施し、病苦を減退して安楽に往生させたいとのことでした。姉上と看護婦は病院に付き添い、自分は毎日あるいは隔日に見舞いに行き病人を慰めていたが、生者必滅会者定離の理にもれず、7月22日ついに眠るがごとく不帰の客となられました。(P.27)
その時の悲しみは紙筆の及ぶところではなく、7月25日にはニューヨークの聖パトリック教会で盛大荘厳の葬式があり、式の後は市外のウッドローン墓地に野辺送りを行い、7月30日に涙とともに遺髪を持って帰朝の途に着きました。(P.27)
譲吉の死を悼み、メリーウォルド、金沢、三共株式会社などゆかりのある土地や企業では半旗が掲げられ、ニューヨークヘラルド紙は「米国は得難き友人を、世界は最高の科学者を失った」と報じました。譲吉の死は、米国現地でも大変惜しまれました。聖パトリック教会の葬儀には600人を超える人が参列し、そのうちの半数が米国人でした。
帰朝の洋上、日本到着の前日は、夜になるまで時々甲板に出かけては我が国の沿岸を眺めていました。彼は何々、此は何々と自分の国を船中から眺望するのは愉快でしたが、これが一生の初めてでまた最後の経験だと思うと、亡き兄が生前何十回となくこの洋上を往復していたことを思い出し、最後に一回自分とともに帰朝できたなら、この楽しい程度が違ったのにと連想すると気分も陰鬱となり涙がこぼれました。(P.67)
亡兄の遺髪を捧持しての帰朝ゆえ、東京駅には塩原氏始め三共株式会社の関係の方々も出迎えられ、感謝の言葉とともに暗涙を呑む姿となりました。遺髪は田口君が塩原家に持参し、仏壇に安置され、他日青山墓地に埋葬の予定です。一度自宅に戻った後、同日夜に塩原家を訪問しニューヨークの話をお伝えしました。(P.68)
往復4か月間を費やした聊か悲しき旅行を拙き筆に記すことにした。
大正11年秋日 竹橋順子(P.27)
世界的に有名な兄を持ち、その最後を外国の地で看取る。本人も書いていますが、竹橋順子にとっては一生に一度の大変な出来事だったのではないでしょうか。年を取っても変わらぬ高峰家の兄弟姉妹の関係性を確認するとともに、「妹に看病に来てほしい」という譲吉の人間的な一面を知ることができる貴重な書物だと思います。
研究会は、高峰譲吉に関する資料及び情報を収集し整理しています。些細なことでも何か情報がありましたらこちらの「お問合せ」から是非お知らせ頂けますと幸いです。
(作成:令和5年6月14日/文責:事務局)